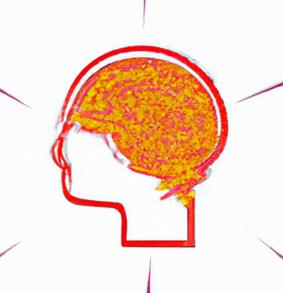
てんかんは医学的には脳の一部が過剰に興奮することで発作が起こる神経疾患です。1920~30年代の優生学の広まりは、てんかんを持つ人々に対して深刻な影響を与えました。てんかんは「遺伝性疾患」の一つとみなされ、社会的に隔離される対象とされることがありました。一部の文化では、てんかんの発作が「悪霊に取り憑かれた」「神の罰」であると誤解され、宗教的な意味付けをされることがありました。当時、てんかんは精神病や異常行動と関連付けられることが多く、一部では「危険人物」とみなされることもありました。てんかんを持つ人々は、結婚や就職の面で不利な扱いを受けることが多くありました。一部の国では、てんかんの人々に対して結婚や出産を禁じる法律が制定されることもありました(例: ドイツやアメリカでは20世紀初頭に「優生学」の観点からこのような政策が取られることがありました)。
特定のタイプのてんかん発作を抑制するために、右脳と左脳を切り分ける手術(脳梁離断術)は有効な外科的治療法です。脳梁離断術を行うと、「分離脳」と呼ばれる状態になる。1940年代にアメリカで初めて実施され、1960年以降、スペリーとその教え子マイケル・ガザニガが、分離脳となった人を対象に様々な実験を行った。この手術は、てんかんによる異常放電が一方の脳半球からもう一方の脳半球に及ばないようになるため、てんかんの症状の緩和した。右脳と左脳が分離している状態では、左右の大脳半球が独立して機能し、以下のような興味深い現象が観察される:
- 左手で持った物の名前が言えない:
右視野にあるもの(左脳で処理される)は言語化できるが、左視野にあるもの(右脳で処理される)は言葉で表現できないため、右脳(左手を制御)が物を認識しても、左脳の言語中枢に情報が伝わらない。 - 左右の脳で異なる判断:
例えば、左視野(右脳)に「雪景色」、右視野(左脳)に「鶏の足」の写真を見せると、関連する物として左手は「スコップ」を、右手は「鶏」を選ぶ。 - 行動の矛盾:
服を着るときに、片方の手がズボンを上げようとし、もう片方が下げようとするなど。 - 作話現象:
左脳が、右脳の動機づけた行動を合理的に説明しようとする。 - 好みの違い:
将来の仕事について、聞かれたときと書いたときで異なる答えをする。
これらの現象は、1つの体に2つの独立した意識が存在するかのような状態を示している。ただし、分離脳患者でも日常生活に大きな支障はなく、脳のより下位の部分で左右の協調が行われていると考えられる。
2. 言語と非言語の分離
- 左脳は一般的に言語や論理的思考を担当するため、言語化に影響する。
- 右脳は空間認識や感情処理、創造的な思考を担当するため、これらの機能は主に非言語的な形で発揮される。
3. 感情の処理
- 左脳と右脳が独立した感情の処理を行うため、一部の感情が意識的に認識されにくくなることがある。
実生活での影響
- 日常生活は比較的問題なく送れることが多い。ただし、極端な状況下や特定の課題において、左右の脳の分離による制限が現れる。
- 例えば、左脳が「ペン」と認識しても、右脳はそれを描く能力に頼るしかなく、言語的に説明できない。
実験例
心理学者のロジャー・スペリーは、スプリットブレイン患者を研究し、この現象を詳細に記録しました。この研究は脳の各部位の機能分化を理解する上で重要な役割を果たしました。
面白い点
- この状況下では、右脳が「独立した意識」を持つように見える場合がある。例えば、右脳が左手を通じて「独自の意志」を示すことがある。
ただし、脳梁を切断することは非常に特殊な医療的手段であり、通常の脳の機能を研究するために行われるものではありません。
1. 初期研究:スペリーとガザニガの実験
概要
ロジャー・スペリーとマイケル・S・ガザニガは、脳梁切断術を受けた患者を対象に分離脳の研究を行いました。この研究は、脳機能の局在性や半球間の情報伝達の重要性を明らかにしました。
主な実験結果
- 視覚情報の分離: 左視野(右脳)に提示された物体を言語で説明することはできないが、左手(右脳制御)でその物体を正しく選ぶことが可能。
- 作話: 左脳(言語を司る)が、右脳が行った行動を合理的に説明しようとする作話行動が観察されました。例えば、右脳の指示で左手が物体を選んだ際に、その理由を創作するケース。
- タキストスコープを使った実験: 短時間で左右の視野に異なる刺激を提示し、それぞれの脳半球がどのように情報を処理するかを測定しました。この手法により、右脳が視覚刺激を認識しても言語化ができないことが確認されました。
意義
この研究は、右脳が言語以外の情報(空間認知や形態認識)に優れていることや、左右半球が異なる役割を持つことを明確にしました。
2. 情報処理メカニズムの解析
概要
最近の研究では、分離脳の情報処理を詳細に解析するため、情報量解析や脳内ネットワークモデルが使用されています。
具体的な研究例
- 脳活動の情報量解析: 研究者は、動物モデル(ラットなど)を使って、脳梁が切断された状態での脳内の情報フローを解析しました。自然発生的な活動と外部刺激による反応の違いを比較することで、脳梁が情報伝達に果たす役割を定量化しています。
- 視覚-運動連携の研究: 左右半球が分離された状態でも、運動や認知タスクを通じてどの程度協力できるのかを評価。右脳は非言語的な判断で優れているため、左手でのタスク成績が右手を上回るケースも報告されています。
意義
このアプローチは、脳内ネットワークの情報処理の効率や冗長性、そして意識の統合的な仕組みの解明に寄与しています。
3. 意識と自我の分断に関する研究
概要
分離脳患者の行動は、「左右の脳半球がそれぞれ独自の意識を持つかのように振る舞う」現象を示すことがあります。この観点から、意識や自我の統一性についての新しい視点が得られています。
観察例
- エイリアンハンド症候群: 片手が、もう片方の手とは独立して行動するケース。患者自身がその動きを「自分の意志ではない」と感じることもあります【9】。
- 動機の分断と作話: 左右半球で異なる目標を持つことが観察され、特に右脳が行った行動を左脳が「理由づけ」しようとする場面が注目されています。この現象は、「意識がどのように一体化しているか」を考える上で重要です。
意義
この研究は、意識の神経相関や情報統合理論(IIT)など、現代の意識研究に大きな影響を与えています。
